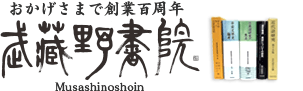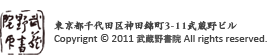ホーム > 書籍案内 > 話題の本(おすすめ) > 小林賢次著作集 第三巻
研究書(語学系) 詳細
小林賢次著作集 第三巻
狂言台本の研究とことば(その一)
| 書名かな | こばやしけんじちょさくしゅう だいさんかん きょうげんだいほんのけんきゅうとことば(そのいち) |
|---|---|
| 著者(編者)名 | 小林千草 編 賢草日本語研究会 監修 |
| 著者(編者)名かな | こばやしちぐさ へん けんそうにほんごけんきゅうかい かんしゅう |
| ISBNコード | 978-4-8386-0812-6 |
| 本体価格 | 11,000円 |
| 税込価格 | 12,100円 |
| 判型 | A5判上製カバー装 |
| 頁数 | 446頁 |
| 刊行日 | 2025年10月29日 |
| 在庫 | 有り |
凡例
序章 狂言のことば
序章 狂言のことば
─その特質と研究状況─
一 はじめに
二 狂言の歴史と台本の成立
三 本書で資料とした狂言台本の底本等
四 狂言のことばの研究状況
第Ⅰ部 狂言台本の資料性の考察
第一章 言語資料としての天理本『狂言六義』
第一節 『狂言六義』上巻から下巻にかけての言語の変容
第一章 言語資料としての天理本『狂言六義』
第一節 『狂言六義』上巻から下巻にかけての言語の変容
一 はじめに
二 ゴザアル・ゴザル等の分布と用法
二・一 ゴザアルとゴザル
二・二 ゴザナイとゴザラヌ
二・三 オリャル・オヂャル・オリナイ
三 マラスル・マスルの分布と用法
四 サラバ・サアラバとソレナラバ
五 おわりに
第二節 「本文」「抜書」の成立とその詞章
第二節 「本文」「抜書」の成立とその詞章
一 はじめに
二 「本文」と「抜書」との関係
三 「本文」と「抜書」の筆録者をめぐって
四 「本文」と「抜書」共通詞章の異同について
五 おわりに
第三節 『狂言六義』の筆録者再考
一 はじめに
二 〔C〕〔D〕〔E〕の筆跡と和泉家古本「抜書」の筆跡の検討
三 問題点の検討
四 おわりに
第二章 言語資料としての和泉家古本『六議』
一 はじめに
二 ゴザアル・ゴザル等の用法
二・一 ゴザアルとゴザル
二・二 ゴザナイとゴザラヌ
二・三 オリャル・オヂャル・オリナイ
三 マラスル・マスルの用法
四 サラバ・サアラバとソレナラバ
五 おわりに
第三章 『大 蔵虎寛本能狂言』における衍字・脱字の校訂について
一 はじめに
二 衍字の校訂について
三 脱字の校訂について
三・一 語の一部を補入したもの
三・二 一語全体を補入したもの
四 おわりに
第Ⅱ部 狂言台本を対象とする語彙・語法の研究
第四章 話す行為を表すことばの待遇的考察
─大蔵虎明本を中心に─
一 はじめに
二 尊敬表現に関して
三 いわゆる謙譲表現(受け手尊敬)に関して
四 おわりに
第五章 天理本『狂言六義』の用語
一 はじめに
二 近世的用語・俗語的用語
二・一 前世(ゼンゼ)
二・二 はっさい〔発才〕
二・三 時刻
二・四 あせらかす
二・五 ありやかる〔有り明かる〕
二・六 負ひ越やす
二・七 かぶらかす
二・八 きする〔たたく、の意〕付、病ます
二・九 取り替ふる
二・一〇 さんばい
二・一一 たて物
二・一二 のどびえ
二・一三 人そばへ
二・一四 振り当たり
二・一五 〔妻の呼称〕妻ぢゃ者・宿守・子持ち・かか(嚊)
二・一六 〔代名詞〕あん(に)・うぬし・これん
三 四段活用動詞+サセラルル
四 おわりに
第六章 版本狂言記の言語
第一節 二段活用の一段化
一 はじめに
二 会話文の場合
二・一 上二段活用動詞の一段化
二・二 終止・連体形と已然形
二・三 助動詞の一段化
二・四 語による一段化傾向の遅速
三 謡・語り及びト書きの場合
四 おわりに
第二節 ゴザル・オリャル・オヂャルとその否定表現形式
一 はじめに
二 ゴザル・ゴザアル・ゴザナイの分布と用法
二・一 ゴザアルとゴザル
二・二 ゴザリマス(ル)とマシテゴザル
二・三 ゴザナイとゴザラヌ
三 オリャル・オヂャル・オリナイの分布と用法
三・一 ゴザルとオリャル・オヂャル
三・二 オリャルとオヂャル
三・三 オリナイ・オリャラヌ・オヂャラヌ
四 おわりに
第七章 固定期狂言台本における「ゴザリマスル」
一 はじめに
二 ゴザリマスルの出現と発達
三 大蔵流台本におけるゴザルとゴザリマスル
三・一 虎寛本・山本東本・茂山家本の場合
三・二 大蔵八右衛門派台本の場合
四 和泉流・鷺流台本におけるゴザルとゴザリマスル
五 おわりに
第八章 大蔵虎光本狂言集の本文の異同について
第一節 待遇表現に関して
一 はじめに
二 虎光本系諸本とその性格
三 丁寧語に関する異同について
三・一 ゴザルとゴザリマスル
三・二 ゴザルとオリャル
三・三 マスル
四 尊敬語・謙譲語に関する異同について
四・一 シメ・サシメ
四・二 ル・ラルとセラル・サセラル、その他
四・三 代名詞・接頭語、その他
五 おわりに
第二節 文法的事象に関して
一 はじめに
二 仮定条件の接続詞について
三 語形の異同
三・一 活用形等
三・二 音便形
四 助動詞・助詞の異同
四・一 助動詞ウ・ウズ及びヌとン
四・二 格助詞
四・三 係助詞
四・四 接続助詞
四・五 終助詞
五 おわりに
第三節 疑問詞疑問文における終助詞「ゾ」
一 はじめに
二 狂言台本における疑問詞疑問文
三 疑問断定表現について
三・一 A型の場合
三・二 B型の場合
三・三 C型の場合
四 平叙疑問表現について
四・一 D型の場合
四・二 E型の場合
四・三 F型の場合
五 おわりに
第Ⅲ部 狂言台本その他を資料とする語史・語法史研究
第九章 「ウゴク(動)」と「ハタラク(働)」
─中世における意味変化を中心に─
一 はじめに
二 「ウゴク」「ハタラク」の成立と意味関係
三 中世における「ウゴク」「ハタラク」
三・一 『今昔物語集』の「動」字の訓
三・二 説話集その他における様相
三・三 「動」字の訓と「働」字の成立
三・四 軍記等における展開
四 《労働》の意味の成立と「ハタラク」の意味変化
五 おわりに
第十章 慣用表現の成立と展開
第一節 「憎まれ子世にはばかる」考─ハバカル・ハビコル・ハダカル─
一 はじめに
二 ハバカルの意味解釈
三 ハバカル・ハビコルの語史
四 ハダカルとの関連
五 おわりに
第二節 「真っ赤な嘘」考─マッカナ・マッカイナ・マッカイサマナ─
一 はじめに
二 「マッカナ嘘」と「マッカイナ嘘」
三 マッカヘサマ・マッカイサマ
四 マッカイナの成立と意味の変容
五 おわりに
第三節 「(言わ)んばかり」考─成立過程と現代語への流れ─
一 はじめに
二 「ンバカリ」の解釈
三 「ヌバカリ」等諸形式の成立と発達
四 近代語における「ヌバカリ」「ンバカリ」等
五 「ム∨ン」「ヌ∨ン」の変化による同音衝突
終章 まとめ
引用・参照文献
小林賢次自筆書き入れより(編者の解説を含む)
所収論文の掲載書籍・雑誌一覧(第三巻)
本書所収の論文解説と未来への展望
本書所収の論文解説と未来への展望
編者のことば
賢草日本語研究会より御礼のことば